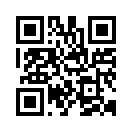2017年11月02日
直進してみると
少し静かになりつつあるが、脅しをかけ合っている国同志を直線で繋いで見た。
その国の首都にある空港から目的地の西海岸L・Aに向けて真っ直ぐに飛んで行くとどのようなコースになるのだろうということが疑問だったからである。

あるソフトで航路を描いてみた。 そうすると北海道の上を通るのではなく、色々と庇ってくれているR国の上を通らなければその目的地には行けそうに無い。
増してや目的国の首都を目標にするのであればもっと北のルートにならざるを得ない。
既に 二度もその国の飛翔体は北海道の上空を通り過ぎたが、その先にはその国が槍玉にあげている相手国は無い。
遠回りをして少しづつカーブさせながら飛ばすことが出来るのかどうかは 正直なところ調べきっていないのでなんとも言えない。
私もたまにこのような検証を見ることがあるのでひとまずは この画像を載せておきたい。
☆ 海外などのネット不可の所でも 電子化した辞書は助けになります ☆
その国の首都にある空港から目的地の西海岸L・Aに向けて真っ直ぐに飛んで行くとどのようなコースになるのだろうということが疑問だったからである。

あるソフトで航路を描いてみた。 そうすると北海道の上を通るのではなく、色々と庇ってくれているR国の上を通らなければその目的地には行けそうに無い。
増してや目的国の首都を目標にするのであればもっと北のルートにならざるを得ない。
既に 二度もその国の飛翔体は北海道の上空を通り過ぎたが、その先にはその国が槍玉にあげている相手国は無い。
遠回りをして少しづつカーブさせながら飛ばすことが出来るのかどうかは 正直なところ調べきっていないのでなんとも言えない。
私もたまにこのような検証を見ることがあるのでひとまずは この画像を載せておきたい。
☆ 海外などのネット不可の所でも 電子化した辞書は助けになります ☆
2015年07月29日
軽飛行機搭乗心得7-重量制限
この記事をずっと前から載せるつもりでいたが、以前に計算した資料が見つからず今に至ってしまった。
軽飛行機は何人乗り、燃料はどのぐらい積めて、最高どのぐらい飛んで行けるかなどとスペックによく書いてある。
しかし、これは鵜呑みには出来ない。
飛行機には最大離陸重量と言う制限があり、私も幾度となく抱えた問題だ。 一番ポピュラーな4人乗りセスナのC172でも同じことで その為に仮の計算をした事がある。
飛んでいたアメリカの成人の標準的体重とされる180ポンド(約82kg)の人3人を乗せて私の当時の体重150ポンド(68Kg)が飛ぶ場合にどうなるか。 平均的な荷物10Kg程度は持ってくるだろうから、それも足して最大離陸重量から引き算してみたら、なんと燃料の4割近くを下ろさなければ飛べないということがわかった。そうなれば800キロメートル行けるところが途中で着陸して給油ということになる。
あとは私がBMI20の115ポンド(51Kg)まで減量すれば あと40分程長く飛べるという事までは調べてみた。無論ゴルフバックなどは積めない! と言うその資料の記憶があるのだが現在見つかっていない。

注: (財)日本航空協会発行の著書 “飛行機の知識”より引用。 原画は連邦航空局のもののようです。
増してや、気温が高くなればなるほど空気の密度が減る(=高い標高の空港に居るのと同じになる)という事になるので、離陸は余計に長く難しいものになる。 カネ払って飛ぶんだから何でも持って行こうとすると このような問題にぶつかる。
旅客機はさすがにジェットなどの洗練されたエンジンを積んでいるが、自家用などで使う小型飛行機は“得るもの”と“失うもの”の選択を迫られるので注意していただきたい。
私の経験でも、5月のアメリカで、かなり暖かくなった日に現地の試験官を同乗させて飛んだことがある。 その人は元々2人乗りのセスナ(C150)は他人を載せることが出来ないぐらいの体格の人で、その日だけ私はBMI=20の51Kgということにデッチ上げて離陸前の計算書を提出した。 飛んでみたがとにかく浮上しない! 無理無理で飛んでも差し障りのない空港だったので難無きを得たが、高度を稼ぐのも重労働だった。
最終試験を受けているので それだけでもかなりのプレッシャーだ。 おまけにヘマをやらかすと“何やってんだ!”的なことをあからさまに言う。 一通りの科目をこなしてションボリした気持ちで空港に戻ったところで “オメデトウゴザイマス”と日本語で言われた時には正直なところ泣いた。
飛行機を飛ばすということ自体、様々なプレッシャーがかかってくる。こんな事したら搭乗者は恐がるだろうかとか色々気を遣う。だから今は一人で飛ぶのが一番気が楽、というのが正直なところだ。
気が散ると車輪を仕舞い忘れたり、ひどいときには4気筒エンジンのプラグ8本の内4本を使わずに離陸してしまった事もある。 今日はエンジンのパワーが上がらないし回転もラフなのでどうしたんだろ、なんて思いながら確認したらこのザマだ。
当地タイのフライングクラブは、滑走路が非常に短い上どちらに向いても障害物があるので、4人乗りでも搭乗は3人迄でと言う規則を設けている。4人乗りで離陸する場合には近隣の空港で合流してからということになる。加えて暑さの影響を考えると春分から秋分の間は飛びたくないというのが正直なところだ。
湿度の高い地域では燃料タンク内で空気中の湿気が水滴になり、燃料タンクの下のほうに溜まることがある。 飛ぶ前の点検が甘いとこれを見逃すことも考えられる。 良くあるのが離陸した直後にこの混ざり物ありの燃料が エンジンに到達し “ゴボゴボ”と言う音を立てながら出力低下が発生するという症状で、事故の原因にもなっている。先日の事故の原因はこれのような気がしてならない。
パイロットも “毎日が初日” を念頭に対応を考えなければならない。神様が操縦しているのではないということを忘れずに、特に小型機に搭乗する際には色々と制約もあるということを忘れないで頂きたい。
それにしても、この稿の原稿何処行っちゃったんだろ??
☆ ネガフィルムは変色します 早めにデジタル化して安心ファイリング ☆
2014年06月05日
軽飛行機搭乗心得6-他機確認
今回のテーマは飛行中に他の飛行機がどのように飛んでいるのかがテーマである。 今でこそレーダーやGPSが一般化した時代ではあるが、どうしても目視確認の他機の位置というのが問題になることが多い。 私も経験があるが自分の真下をある航空会社のB737が悠然と横切って肝を冷やしたことがある。
他の飛行機の事を“Traffic”と呼ぶのが一般的である。 その場合に飛行機に搭乗してい時に進行方向を12時方向、右が3時方向というように自分が時計の中心に座っているように表現するのが一般的である。 飛行機の右側に座り“Traffic 4Oclock”と言われたら右後方を見ることになる。 特にパイロットは左の前に座っているので特にその方向が見づらい。 どうかこのようなときは協力して他機の確認をしていただきたい。
特に4時方向は見づらく、航空管制から報告を受けて見回したものの見つからない。 そして同乗者に指摘されたのが既に遥か前方を飛ぶ白いF16がやっと確認できたなどということがあった。 サンダーバーズの単独機が訓練を終えて帰ってきたのだろう。 それにしてもすごいスピードであっという間に消えていった。
特に厄介なのが見える方角が変化しない飛行機で、これがそのまま進むとニアミスや衝突になる危険性を多分に含んでいるというのが一般的に言われていることである。
他にもパラシュートジャンピングのメッカのようなところもあり、うっかりすると飛行機の前を飛んでいる人の顔が識別できるほどの距離を横切ったなどという経験をした事例も聞いていおり正に油断大敵である。 特に大都市の飛行場に近づいたらカーテンなどを自発的に開けてご協力いただきたい。
< ブログランキングに参加しております 下記をひと押し頂ければ幸いです >

にほんブログ村
☆ 先方の情報をスマホで確認 電子化した名刺箱が現場で活躍! ☆
他の飛行機の事を“Traffic”と呼ぶのが一般的である。 その場合に飛行機に搭乗してい時に進行方向を12時方向、右が3時方向というように自分が時計の中心に座っているように表現するのが一般的である。 飛行機の右側に座り“Traffic 4Oclock”と言われたら右後方を見ることになる。 特にパイロットは左の前に座っているので特にその方向が見づらい。 どうかこのようなときは協力して他機の確認をしていただきたい。
特に4時方向は見づらく、航空管制から報告を受けて見回したものの見つからない。 そして同乗者に指摘されたのが既に遥か前方を飛ぶ白いF16がやっと確認できたなどということがあった。 サンダーバーズの単独機が訓練を終えて帰ってきたのだろう。 それにしてもすごいスピードであっという間に消えていった。
特に厄介なのが見える方角が変化しない飛行機で、これがそのまま進むとニアミスや衝突になる危険性を多分に含んでいるというのが一般的に言われていることである。
他にもパラシュートジャンピングのメッカのようなところもあり、うっかりすると飛行機の前を飛んでいる人の顔が識別できるほどの距離を横切ったなどという経験をした事例も聞いていおり正に油断大敵である。 特に大都市の飛行場に近づいたらカーテンなどを自発的に開けてご協力いただきたい。
< ブログランキングに参加しております 下記をひと押し頂ければ幸いです >
にほんブログ村
☆ 先方の情報をスマホで確認 電子化した名刺箱が現場で活躍! ☆
2014年05月15日
乗員@香港空港
数年前、ある航空会社のパイロットと頻繁に会っていた。 そのときに聞いた話としてこんなのがある。
規律のうるさいことで有名な香港の空港に降り、その日はそこで泊まることとなっていた。 そうなるとパスポートを見せて空港の外のホテルに行かなければならない。 本当は持っていたのだが “すみませんパスポートを忘れました。” と言って粘ってみた。 さすがにそれでは入国管理官も通過させてくれない。 とにかくヒラ謝りしてみたら最後に“Please”の一言で通してくれたそうだ。
あのうるさい空港でもこんなこともあるのかと驚いた。 無論、一般乗客は先ず密出国でもしなければできない。 それにしてもそのパイロットの居る国では出発前にパスポート検査の手はずがないのだろうかと気になってしまうところだ。
色々なピンチにも遭って必死に操縦してきた。 誠実な人柄のそのパイロットも今では定年を迎えて故郷で農業をしているとのこと。 訪ねてみたいところだ。
< ブログランキングに参加しております 下記をひと押し頂ければ幸いです >

にほんブログ村
☆ LPなどのレコード、カセットテープの音源をパソコンにお引越し ☆
規律のうるさいことで有名な香港の空港に降り、その日はそこで泊まることとなっていた。 そうなるとパスポートを見せて空港の外のホテルに行かなければならない。 本当は持っていたのだが “すみませんパスポートを忘れました。” と言って粘ってみた。 さすがにそれでは入国管理官も通過させてくれない。 とにかくヒラ謝りしてみたら最後に“Please”の一言で通してくれたそうだ。
あのうるさい空港でもこんなこともあるのかと驚いた。 無論、一般乗客は先ず密出国でもしなければできない。 それにしてもそのパイロットの居る国では出発前にパスポート検査の手はずがないのだろうかと気になってしまうところだ。
色々なピンチにも遭って必死に操縦してきた。 誠実な人柄のそのパイロットも今では定年を迎えて故郷で農業をしているとのこと。 訪ねてみたいところだ。
< ブログランキングに参加しております 下記をひと押し頂ければ幸いです >
にほんブログ村
☆ LPなどのレコード、カセットテープの音源をパソコンにお引越し ☆
2014年04月26日
神隠し検証
東京の実家に居たときに、近所の図書館でこの地域の奇談を集めた本を読んだ。 その中の一話が大正12年の青梅市で起きた奇妙な事件のことである。
9月に関東大震災が起きるが、その直前の7月のある日の早朝に地元の人が草刈をしていると 一人の女の子の鳴き声が聞こえた。 何で泣いているのか尋ねても言葉が通じない。 この人の知り合いが青梅鉄道の日向和田駅の駅長のためそこへ連れて行き相談した。 見当をつけたのが東北方面の子供ではないかということで、鉄道電話で立川を通じて上野、米沢、仙台、盛岡などに問い合わせをした。
すると盛岡から、昨日の夕方からある村の女児が行方不明になっていて 村を挙げて探しているとの返事が返ってきた。 確認が取れたので首から札(名前と下車駅を記載)を下げて結び飯を沢山持たせられた格好で送り返された。ご両親からもお礼の手紙が届いたとの事だが高速も新幹線も無い時代にどうやってここまで移動できたのだろう? 残るは飛行機しかないと思い、シミュレータで試してみた。

岩手からこの青梅市を結ぶルートであれば当時は只の空き地だったかもしれないが、花巻空港と横田飛行場(基地)が妥当ではないだろうか?
距離:441Km。 途中の山を越すには3,000メートルの高度が妥当。 飛行機の機種はその当時を彷彿させるパイパー社のCub。
“こぐま”のように可愛いが、3時間の飛行しか出来ない。速度も毎時137Km程度。 高度を上げて飛ぼうとするとグラウンド・スピード(地上における速度)がどんどん下がるような上空の風向きだ。 そうなると低空で山を避けて飛ぶしかない。そうなると余計に飛行距離が伸びるという悪循環、どうやっても3時間30分はかかるので途中で燃料切れになる。
おまけにこの当時、夜間に飛べるような環境があったのだろうか? 前日の夕方まで岩手にいたということは 夜間に移動しなければ翌朝に東京の西のはずれには到底たどり着けない。
その娘のご両親からお礼の手紙が届き ”一体どうやってそこまで行けたんだろう” との一文。
昔なら”天狗様のお戯れ”で解決だが、どうなんだろう?
又、この女の子がどのような人生を送ったのかも調べてみたいところである。
< ブログランキングに参加しております 下記をひと押し頂ければ幸いです >

にほんブログ村
☆ 書棚の書籍やメディアはポケットに入れて持ち歩こう ☆
9月に関東大震災が起きるが、その直前の7月のある日の早朝に地元の人が草刈をしていると 一人の女の子の鳴き声が聞こえた。 何で泣いているのか尋ねても言葉が通じない。 この人の知り合いが青梅鉄道の日向和田駅の駅長のためそこへ連れて行き相談した。 見当をつけたのが東北方面の子供ではないかということで、鉄道電話で立川を通じて上野、米沢、仙台、盛岡などに問い合わせをした。
すると盛岡から、昨日の夕方からある村の女児が行方不明になっていて 村を挙げて探しているとの返事が返ってきた。 確認が取れたので首から札(名前と下車駅を記載)を下げて結び飯を沢山持たせられた格好で送り返された。ご両親からもお礼の手紙が届いたとの事だが高速も新幹線も無い時代にどうやってここまで移動できたのだろう? 残るは飛行機しかないと思い、シミュレータで試してみた。

岩手からこの青梅市を結ぶルートであれば当時は只の空き地だったかもしれないが、花巻空港と横田飛行場(基地)が妥当ではないだろうか?
距離:441Km。 途中の山を越すには3,000メートルの高度が妥当。 飛行機の機種はその当時を彷彿させるパイパー社のCub。
“こぐま”のように可愛いが、3時間の飛行しか出来ない。速度も毎時137Km程度。 高度を上げて飛ぼうとするとグラウンド・スピード(地上における速度)がどんどん下がるような上空の風向きだ。 そうなると低空で山を避けて飛ぶしかない。そうなると余計に飛行距離が伸びるという悪循環、どうやっても3時間30分はかかるので途中で燃料切れになる。
おまけにこの当時、夜間に飛べるような環境があったのだろうか? 前日の夕方まで岩手にいたということは 夜間に移動しなければ翌朝に東京の西のはずれには到底たどり着けない。
その娘のご両親からお礼の手紙が届き ”一体どうやってそこまで行けたんだろう” との一文。
昔なら”天狗様のお戯れ”で解決だが、どうなんだろう?
又、この女の子がどのような人生を送ったのかも調べてみたいところである。
< ブログランキングに参加しております 下記をひと押し頂ければ幸いです >
にほんブログ村
☆ 書棚の書籍やメディアはポケットに入れて持ち歩こう ☆
2014年04月13日
軽飛行機搭乗心得5-操縦装置
今回もパイロットの隣に座ったときに気をつけなければならないことについてである。そんなに簡単に操縦関係の装置に触れようとする人はいないだろうが念のために書いておきたい。
フロントパネルにはいろいろなレバーがついている。 意外と認識しやすいようにレバーの形状をその目的物の形にしていることが多い。車輪はタイヤの形に、フラップもその形状に似せてレバーを設計している。
しかし、この二つは決められて速度より遅い時しか操作してはならないことになっている。 車輪のレバーは一度引っ張ってからでないと操作できないような安全対策が施されている。 しかしフラップはそうではなく簡単に操作できることが多い、それも電動モーターで意図も簡単に操作できる。 それが規定以上の速度で操作した場合には壊れても保障できないというように飛行機メーカーは発表している。
こんなところにコンビニ袋を提げるところがあるなんて思う人はいないだろう。 しかし何らかのものがレバーに触れると一大事である。
パイパー社の一部の飛行機には電動フラップの装置がなく、自動車のサイドブレーキのようなレバーで人力で操作するようなものもある。 よってその“サイドブレーキ”のレバーのところに物があると操作も出来なくなってしまう。
またグラマン社の飛行機にもフラップの操作レバーが意外なところにあって操作するのに驚いたことがある。それも座席と座席の間に小さなレバーが隠れているような取り付け方だ。
足元にも燃料タンクの切り替えレバーがあることも多々ありややこしさを助長している。 前席に座るチャンスに恵まれても色々と見回してからフライトすることをお勧めする。
< ブログランキングに参加しております 下記をひと押し頂ければ幸いです >

にほんブログ村
☆ 個人蔵書、名刺、書類などの電子化 お任せください ☆
フロントパネルにはいろいろなレバーがついている。 意外と認識しやすいようにレバーの形状をその目的物の形にしていることが多い。車輪はタイヤの形に、フラップもその形状に似せてレバーを設計している。
しかし、この二つは決められて速度より遅い時しか操作してはならないことになっている。 車輪のレバーは一度引っ張ってからでないと操作できないような安全対策が施されている。 しかしフラップはそうではなく簡単に操作できることが多い、それも電動モーターで意図も簡単に操作できる。 それが規定以上の速度で操作した場合には壊れても保障できないというように飛行機メーカーは発表している。
こんなところにコンビニ袋を提げるところがあるなんて思う人はいないだろう。 しかし何らかのものがレバーに触れると一大事である。
パイパー社の一部の飛行機には電動フラップの装置がなく、自動車のサイドブレーキのようなレバーで人力で操作するようなものもある。 よってその“サイドブレーキ”のレバーのところに物があると操作も出来なくなってしまう。
またグラマン社の飛行機にもフラップの操作レバーが意外なところにあって操作するのに驚いたことがある。それも座席と座席の間に小さなレバーが隠れているような取り付け方だ。
足元にも燃料タンクの切り替えレバーがあることも多々ありややこしさを助長している。 前席に座るチャンスに恵まれても色々と見回してからフライトすることをお勧めする。
< ブログランキングに参加しております 下記をひと押し頂ければ幸いです >
にほんブログ村
☆ 個人蔵書、名刺、書類などの電子化 お任せください ☆
2014年04月09日
フツーの機長
隣国での航空機行方不明のニュースもほとんど影をひそめてしまった現在である。 飛行機を操縦する人はどんな人格なのかということも考えることもあるだろう。 今までに出会った人の話を総合すると、次のようなことがまとめられる。
先ずは大雑把で上位2桁の計算をする程度で事を進める。 こだわるととことんこだわるオタクタイプだが 興味の対象外になるとどうでも良くなる。 血液型ではO型のタイプのようだし 聞いて回ると殆どそのようなことが多かった。
あとは大酒のみ、ヘビースモーカー、女好きというのが定番だ。 これがヘリコプターになると酒の量はハンパではない。 それに“大言壮語”のおまけが付くのがお約束だ。 その点固定翼パイロットは比較的無口だ。
しかし憧れのパイロットになるためには教育を受けなければならない。そのためにも自分で勉強することも重要なポイントとなる。一般的に一番難しいのが計器飛行操縦の課程だ。 これは非常に苦痛で機外が見えないようなバイザーをかぶせられて操縦訓練をする。 運転をされる方で濃霧の中を両サイドの白線を頼りに恐々、その中を通り抜けたことがあれば、計器飛行と同じような経験をされたことになる。
能力の限界に挑むような状態なのでどんなに優秀な人でも若干おかしくなる。 そんな先輩の中で語り継がれているのが、この計器飛行訓練の最終テスト飛行で進路を70度も間違えて一発で不合格を食らったということを聞いたことがある。勿論私も人のことは言えないのは無論だ。
但し 安全と人命については徹底した教育を受ける。 一旦離陸した飛行機は着陸させなければならない。それも疲れ果てた頃にその作業をすることになる。 だから安全に作業を出来ないと免許も下りないし、一人前とは認められない。正に洗脳と言えるほどの課程を経なければならない。
使っている機体に関しても取り扱い、保守、点検は徹底して叩き込まれる。システムも概要を把握していなければ 何か不具合が生じたときに対応できないので理解度を試される。 但しメンテナンス部門は非常に奥が深いのでこれでメシを食おうという覚悟がない人は手を出さなかった。
思い入れのある人の自転車や自動車と同じで、土足厳禁のステッカーを貼って運転している人はこのパイロット的な思い入れのある人たちと通じるところが多いと思える。 自分の命を支えて思うように動いてくれる飛行機も自動車も自転車も“私の恋人です”と堂々と言えるのが共通点だと断言できる。
< ブログランキングに参加しております 下記をひと押し頂ければ幸いです >

にほんブログ村
☆ LPなどのレコード、カセットテープの音源をパソコンにお引越し ☆
先ずは大雑把で上位2桁の計算をする程度で事を進める。 こだわるととことんこだわるオタクタイプだが 興味の対象外になるとどうでも良くなる。 血液型ではO型のタイプのようだし 聞いて回ると殆どそのようなことが多かった。
あとは大酒のみ、ヘビースモーカー、女好きというのが定番だ。 これがヘリコプターになると酒の量はハンパではない。 それに“大言壮語”のおまけが付くのがお約束だ。 その点固定翼パイロットは比較的無口だ。
しかし憧れのパイロットになるためには教育を受けなければならない。そのためにも自分で勉強することも重要なポイントとなる。一般的に一番難しいのが計器飛行操縦の課程だ。 これは非常に苦痛で機外が見えないようなバイザーをかぶせられて操縦訓練をする。 運転をされる方で濃霧の中を両サイドの白線を頼りに恐々、その中を通り抜けたことがあれば、計器飛行と同じような経験をされたことになる。
能力の限界に挑むような状態なのでどんなに優秀な人でも若干おかしくなる。 そんな先輩の中で語り継がれているのが、この計器飛行訓練の最終テスト飛行で進路を70度も間違えて一発で不合格を食らったということを聞いたことがある。勿論私も人のことは言えないのは無論だ。
但し 安全と人命については徹底した教育を受ける。 一旦離陸した飛行機は着陸させなければならない。それも疲れ果てた頃にその作業をすることになる。 だから安全に作業を出来ないと免許も下りないし、一人前とは認められない。正に洗脳と言えるほどの課程を経なければならない。
使っている機体に関しても取り扱い、保守、点検は徹底して叩き込まれる。システムも概要を把握していなければ 何か不具合が生じたときに対応できないので理解度を試される。 但しメンテナンス部門は非常に奥が深いのでこれでメシを食おうという覚悟がない人は手を出さなかった。
思い入れのある人の自転車や自動車と同じで、土足厳禁のステッカーを貼って運転している人はこのパイロット的な思い入れのある人たちと通じるところが多いと思える。 自分の命を支えて思うように動いてくれる飛行機も自動車も自転車も“私の恋人です”と堂々と言えるのが共通点だと断言できる。
< ブログランキングに参加しております 下記をひと押し頂ければ幸いです >
にほんブログ村
☆ LPなどのレコード、カセットテープの音源をパソコンにお引越し ☆
2014年04月06日
軽飛行機搭乗心得4-ペダル
今回の話はパイロットの隣に座った場合の話だ。 殆どの固定翼飛行機には左側の席がパイロットの席となる。 そうなると どうしても日本で車を運転していたときの記憶が甦ってくる。
そんなときに一番気を付けていただきたいのが、前にある二つのペダルを無意識に踏まないでもらいたい。 この二つのペダルは下部を踏むと方向陀になり右へ踏むと右へという風に設計されている。 またペダルの上部を踏むと主輪のブレーキが効くようになっており、特に双発機などは かなり強力なブレーキが利く。
実際にあった事故では パイロットがペダルの上部を無意識に踏んだまま着陸し 足をとられたかたちで着陸と同時にでんぐり返しをご披露してしまったことがある。 幸い火事や人身事故にならなかったがエンジンとプロペラはオシャカで積み替える羽目になってしまった。
無意識に動くことの怖さを思い知らされる事故ではないだろうか? 今のところ事例を耳にしていないが 同乗者による無意識なブレーキの踏み込みによって着陸を乱されることが起きないという保障はないので強く進言したい。
無論、着陸前にブレーキ・リリース・チェックの打ち合わせを確実に行うのが常だが 着陸作業が忙しくて手が回らないことも考えられる。
私も車に同乗したときにドライバーがあまりにもすばらしい運転をすると どうしても右足が疲れる。そんなことがあると 飛行機に搭乗した際についても警鐘を鳴らしておく必要があると常々感じていた。 このブログを通じて“無意識の動作の怖さ”を強くお伝えしておきたい。
< ブログランキングに参加しております 下記をひと押し頂ければ幸いです >

にほんブログ村
☆ 引越しの強い味方です 書籍、書類の電子化 ☆
そんなときに一番気を付けていただきたいのが、前にある二つのペダルを無意識に踏まないでもらいたい。 この二つのペダルは下部を踏むと方向陀になり右へ踏むと右へという風に設計されている。 またペダルの上部を踏むと主輪のブレーキが効くようになっており、特に双発機などは かなり強力なブレーキが利く。
実際にあった事故では パイロットがペダルの上部を無意識に踏んだまま着陸し 足をとられたかたちで着陸と同時にでんぐり返しをご披露してしまったことがある。 幸い火事や人身事故にならなかったがエンジンとプロペラはオシャカで積み替える羽目になってしまった。
無意識に動くことの怖さを思い知らされる事故ではないだろうか? 今のところ事例を耳にしていないが 同乗者による無意識なブレーキの踏み込みによって着陸を乱されることが起きないという保障はないので強く進言したい。
無論、着陸前にブレーキ・リリース・チェックの打ち合わせを確実に行うのが常だが 着陸作業が忙しくて手が回らないことも考えられる。
私も車に同乗したときにドライバーがあまりにもすばらしい運転をすると どうしても右足が疲れる。そんなことがあると 飛行機に搭乗した際についても警鐘を鳴らしておく必要があると常々感じていた。 このブログを通じて“無意識の動作の怖さ”を強くお伝えしておきたい。
< ブログランキングに参加しております 下記をひと押し頂ければ幸いです >
にほんブログ村
☆ 引越しの強い味方です 書籍、書類の電子化 ☆
2014年03月25日
軽飛行機搭乗心得3-扉
通常の旅客機と違い機体はかなり華奢に出来ているのが実情である。 よって離陸などGのかかる飛行時にとんでもないことが起こることがある。 それは閉めたはずのドアが開くということである。
特に高翼機の場合は主翼にぶら下がるため機体が変形しやすく、ドアの開いてしまうことが多々ある。 ハンパではない風で、再度閉めなおすにもかなりの力が必要なところである。
一番 気をつけていただきたいのはドアの近辺に物を置かないということである。 飛ばしている本人も地図などは最初のうちは出さないで仕舞っておき ある程度の高度が確保できたところで広げるというのが常だった。
古い機体で飛ぶことが多かったのでこのようなことは日常茶飯事だった。 最新鋭の飛行機などとんとご縁が無いので これは普通のこととして考えている。

又、暑い日とか 煙草を吸うときに窓を開けて飛ぶこともある。 そんなときの風の回り込みもあるのでどのような風が機内を通るかを見ておく必要がある。 さもないと大事な所持品を下界に飛ばしてしまうことになる。
そういえば機内の灰皿はいつも“テンコ盛り”だった。
< ブログランキングに参加しております 下記をひと押し頂ければ幸いです >

にほんブログ村
☆ LPなどのレコード、カセットテープの音源をパソコンにお引越し ☆
特に高翼機の場合は主翼にぶら下がるため機体が変形しやすく、ドアの開いてしまうことが多々ある。 ハンパではない風で、再度閉めなおすにもかなりの力が必要なところである。
一番 気をつけていただきたいのはドアの近辺に物を置かないということである。 飛ばしている本人も地図などは最初のうちは出さないで仕舞っておき ある程度の高度が確保できたところで広げるというのが常だった。
古い機体で飛ぶことが多かったのでこのようなことは日常茶飯事だった。 最新鋭の飛行機などとんとご縁が無いので これは普通のこととして考えている。

又、暑い日とか 煙草を吸うときに窓を開けて飛ぶこともある。 そんなときの風の回り込みもあるのでどのような風が機内を通るかを見ておく必要がある。 さもないと大事な所持品を下界に飛ばしてしまうことになる。
そういえば機内の灰皿はいつも“テンコ盛り”だった。
< ブログランキングに参加しております 下記をひと押し頂ければ幸いです >
にほんブログ村
☆ LPなどのレコード、カセットテープの音源をパソコンにお引越し ☆
2014年03月20日
軽飛行機搭乗心得2-離着陸時
あまり細かいことを言いたくないところだが、 搭乗者や荷物の移動に非常に敏感な乗り物だというのが正直なところだ。 特に離陸と着陸のときは非常に気を使い事前に一言 “機長アナウンス” を入れなければならないこともある。
重心が変われば飛行機の上下方向の向きが変わり、速度や高度も変わってくる。 わかっている人だけで飛んでいる場合には心配ないが、そうでなければ予め注意しておかないと着陸などのときにとんでもないことになる可能性がある。
また、座席が前後方向に動かせる方式のものは離着陸の前に座席が確実に固定されているか確認する必要がある。 これはパイロット側の席での話しだが離陸して機首を上げた途端、座席が後ろにずれて操縦不能になり墜落したケースもあったので、そのため座席の固定の確認は非常に厳しく見ている。
重心がずれてもトリムという装置で意図した迎え角で難なく飛べるようにしているが その操作が間に合わなければそれまでは片手一本で操縦桿を押したり引いたりして前後のバランスをとり、ピッチングを調整しなければならない。 何でそうしなければならないのかの原因がつかめないときはやはり嫌なものだ。 腕が悪いのは承知だが、それ以上に原因を推理しなければならなくなると余計に神経を使うし危険性も増す。
普通 左手一本で機械的なバランス全てをコントロールしている。 その為自分ひとりで飛んでいるときはやはり安心するというのが本音である。
どうか離陸と着陸の際の体重移動や荷物の移動は絶対に避けてほしい。
< ブログランキングに参加しております 下記をひと押し頂ければ幸いです >

にほんブログ村
☆ 先方の情報をスマホで確認 電子化した名刺箱が現場で活躍! ☆
重心が変われば飛行機の上下方向の向きが変わり、速度や高度も変わってくる。 わかっている人だけで飛んでいる場合には心配ないが、そうでなければ予め注意しておかないと着陸などのときにとんでもないことになる可能性がある。
また、座席が前後方向に動かせる方式のものは離着陸の前に座席が確実に固定されているか確認する必要がある。 これはパイロット側の席での話しだが離陸して機首を上げた途端、座席が後ろにずれて操縦不能になり墜落したケースもあったので、そのため座席の固定の確認は非常に厳しく見ている。
重心がずれてもトリムという装置で意図した迎え角で難なく飛べるようにしているが その操作が間に合わなければそれまでは片手一本で操縦桿を押したり引いたりして前後のバランスをとり、ピッチングを調整しなければならない。 何でそうしなければならないのかの原因がつかめないときはやはり嫌なものだ。 腕が悪いのは承知だが、それ以上に原因を推理しなければならなくなると余計に神経を使うし危険性も増す。
普通 左手一本で機械的なバランス全てをコントロールしている。 その為自分ひとりで飛んでいるときはやはり安心するというのが本音である。
どうか離陸と着陸の際の体重移動や荷物の移動は絶対に避けてほしい。
< ブログランキングに参加しております 下記をひと押し頂ければ幸いです >
にほんブログ村
☆ 先方の情報をスマホで確認 電子化した名刺箱が現場で活躍! ☆
2014年03月16日
軽飛行機搭乗心得1-飲食
大型の旅客機は乗る機会がだいぶ多いが、小型機に乗るのはそう多くないのではないだろうか? そうなると気をつけなければならないことも違ってくる。 そんなことで思い出したところから徐々に書き綴っていきたいと思う。
先ず乗る前だが、飲み物は控えたほうが良い。 離陸した途端に気温が下がり体が冷えてどうしても“近く”なってしまうからだ。 1,000メートル上がる毎に6℃下がるのが一般的だから距離を飛ぶ場合には約3,000メートルぐらいは上がるだろうから それだけでも18℃下がる計算になる。
もアメリカで経験があるが、振る舞いコーラを行った先でゴチになり、再び離陸して間もなく“行きたく”なってしまったことがある。 次の目的地までの半分も飛んでいないところであるが 仕方なく地方空港に着陸の手はずをとり、着陸態勢に入った。 これから離陸しようとしている定期旅客便のパイロットが親切な方だったので待っていてくれて、私を優先的に着陸させてくれた。 “ネゴ”に勝ったことを考えてみればあそこには管制塔も無かったことを今思い出した。 あのときの機長様、ありがとうございました。お陰さまでお漏らしなしで“蓮華”にたどり着けました。
そんな迷惑をかけることにもなるので特にコーラなどカフェインの入った利尿効果のある飲み物は気をつけるべきだ。
手元にその当時の教科書が無いので記憶に頼るしかないが、腸内でガスを発生させる効果のある食べ物も摂らない方が良い。 閉め切った機内では“放屁厳禁”だ。 特にキャビン内の空気を直接ジャイロ計器に流すようになっているので そのようなもので“洗礼”を受けたくない。
意外なものではかぶ(ラディッシュ)も そのような食品に含まれていたことを記憶している。
< ブログランキングに参加しております 下記をひと押し頂ければ幸いです >

にほんブログ村
Ⅰ ☆ 個人蔵書、名刺、書類などの電子化 お任せください ☆
先ず乗る前だが、飲み物は控えたほうが良い。 離陸した途端に気温が下がり体が冷えてどうしても“近く”なってしまうからだ。 1,000メートル上がる毎に6℃下がるのが一般的だから距離を飛ぶ場合には約3,000メートルぐらいは上がるだろうから それだけでも18℃下がる計算になる。
もアメリカで経験があるが、振る舞いコーラを行った先でゴチになり、再び離陸して間もなく“行きたく”なってしまったことがある。 次の目的地までの半分も飛んでいないところであるが 仕方なく地方空港に着陸の手はずをとり、着陸態勢に入った。 これから離陸しようとしている定期旅客便のパイロットが親切な方だったので待っていてくれて、私を優先的に着陸させてくれた。 “ネゴ”に勝ったことを考えてみればあそこには管制塔も無かったことを今思い出した。 あのときの機長様、ありがとうございました。お陰さまでお漏らしなしで“蓮華”にたどり着けました。
そんな迷惑をかけることにもなるので特にコーラなどカフェインの入った利尿効果のある飲み物は気をつけるべきだ。
手元にその当時の教科書が無いので記憶に頼るしかないが、腸内でガスを発生させる効果のある食べ物も摂らない方が良い。 閉め切った機内では“放屁厳禁”だ。 特にキャビン内の空気を直接ジャイロ計器に流すようになっているので そのようなもので“洗礼”を受けたくない。
意外なものではかぶ(ラディッシュ)も そのような食品に含まれていたことを記憶している。
< ブログランキングに参加しております 下記をひと押し頂ければ幸いです >
にほんブログ村
Ⅰ ☆ 個人蔵書、名刺、書類などの電子化 お任せください ☆